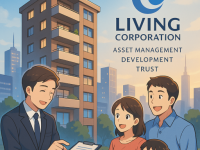保護猫と暮らすという選択 —— 動物OKマンションでかなえる、小さくて大きな幸せ
財務経理ユニットのなかじーです。
ある日、あなたの家の前に、小さな猫が、一匹、うずくまっていたら——。
大きな目でこちらを見上げて。
何かを訴えるように鳴くその声に、胸がきゅっとなる——
そんな経験はありませんか?
日本では、年間およそ2万5千匹もの猫が自治体に保護されているといわれています。
保護される理由はさまざま。飼い主が手放してしまったり、野良として生まれてしまったり。生後間もない子猫もいれば、人に慣れた大人の猫もいます。
私たちが思っている以上に、行き場を失う命は多いのです。
けれど、その一方で、保護猫活動のおかげで、救われる命もたくさんあります。
ボランティアの方々が、病気やケガの手当てをし、人に慣れるように根気よくお世話をしてくれる。里親探しの譲渡会では、元気になった猫たちが新しい家族との出会いを待っています。

あの日、家の前でうずくまっていたあの子も、きっとそんな人たちに手を差し伸べてもらったのでしょう。
私が最初に保護猫を迎えたのは、まだ「ペットと暮らすなんて大変そう」と思っていた頃でした。
帰宅しても真っ暗な部屋で、冷たい空気に迎えられる毎日。けれど譲渡会で出会った一匹の小さな猫に「この子となら、頑張れるかも」と思えたのです。
最初の数日は、彼女は部屋の隅に隠れ、警戒してこちらを見ていました。
それでも、静かにそばに座り、本を読みながら過ごしているうちに、少しずつ距離が縮まっていく。
一週間も経つと、私の膝の上にちょこんと乗り、そこで眠るようになったのです。
あの温もり、あの小さな寝息にどれほど救われたか言葉にできません。
保護猫は、少し臆病な子もいます。

けれど、だからこそ、時間をかけて築いた絆は深く、尊いものになります。
彼女は私の帰りを待つようになり、ドアを開けると小さな足音を響かせて走ってくる。
疲れた日も、悩みがある日も、その小さな命が無条件で迎えてくれるだけで、不思議と元気になれるのです。
もちろん、家族がいる方にとっても、保護猫は大きな存在になります。
動物を育てることで子どもが責任感を持つようになったり、思いやりを学んだりするのは、とても素敵なことだと思います。
休日、家族みんなでリビングに集まり、猫を真ん中にして遊ぶ。
猫は気ままに日なたで寝転び、時々「にゃあ」と一声かける。
そんな、なんでもないけれど特別な時間が、家族をもっと強く結びつけてくれるのです。
一方で、誰にも邪魔されずに過ごす夜、ふと寂しさを感じるときもありますよね。
部屋の灯りをつけると、待っていましたと言わんばかりにしっぽを立ててすり寄ってくる小さな命がそこにいる。
そんな存在がいるだけで、「ただいま」と言える家が、ぐっと温かく感じられるのです。
ソファでくつろいでいると、いつの間にか足元に寄り添って寝ていたり、一緒にベッドに入り、朝は顔をちょんちょんと叩いて起こしてくれる。
そんなひとつひとつの瞬間が、かけがえのない宝物になります。
でも、猫と暮らすには環境も大切です。
ペット禁止の賃貸住宅では、こっそり飼うのは難しく、トラブルの原因にもなります。
「ペット可」と書いてあっても、実際には条件が厳しかったり、動物への配慮の少ない物件もあります。
その点、動物OKマンションなら、安心して一緒に暮らすことができます。周りも動物好きの住人が多いので、気持ちよく過ごせるのも魅力です。
フローリングの傷がつきにくい素材や、脱走防止対策の整った設備がある物件もあり、猫にも飼い主にも優しい環境が整っています。
猫を迎えたいけれど、どんな住まいを選べばいいかわからない方、仕事で忙しいけれど帰ったときに小さな命に迎えてほしい方、子どもに優しさや責任感を学ばせたいと考えているご家族。私たちの会社では、そんなみなさんにぴったりのペットと暮らしやすいペット共生マンションContigoをご用意しています。

一匹の猫を救うことは、決して特別なことではありません。
ほんの少し勇気を出して手を差し伸べることで、その小さな命はあなたの人生を大きく輝かせてくれます。そして、その新しい家族と過ごす日々を、安心して楽しむために、動物OKの住まいを選ぶことも大切です。
私たちはそういうマンションを作っています。
「ただいま」と言える幸せ。
「おかえり」と迎えてくれる温もり。
そんな毎日が、ここから始まります。
ぜひ、保護猫という選択肢を。そして、猫と暮らせるマンションという選択肢を。
私たちは、あなたと新しい家族の出会いを心から応援しています。
きっと、あの子があなたを待っています。
※参考:環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況」